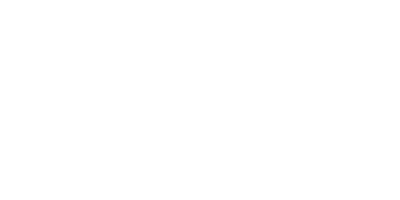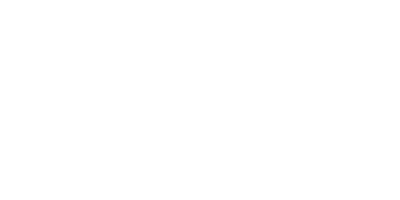祈り
水音
故郷へ、帰ることにしました。
先生がそう言ったのは、ようやく長い冬が去り、木々の枝にふっくらとした若葉が芽吹きはじめる季節のことだった。
先生は、無造作にひっつめた長い黒髪をやわらかな日差しにすかして、とてもおだやかな声で言った。襟元から見える細い首筋に、トーマは思わず目をうばわれた。
「どうして」
言ってしまってから、なんて間のぬけた質問なのだろうと思った。
先生がふらりとアラインズベルにやってきたのは半年前のことだ。
若いおんながひとり。小さな空き家を借りて、静かに住みはじめた。
ひとの顔ぶれにほとんど変わりのない町なかで、先生はたいそう目立った。ちょっとした振る舞いのひとつひとつに、洗練された、都会的な雰囲気があった。おだやかな声音は、ふかい知性をうかがわせた。どこか遠くに思いをはせるように、うわのそらに見えることが、たびたびあった。
わけありに違いないと、ひそひそ話が町のあちこちでされた。ちょうど戦争が終わってしばらく経ったころだったから、もしかしたら、となりの国の”ぼうめいしゃ”なのではないかと言うひともいた。ふしだらなおんなが、都にいられなくなって逃げてきたのだろうと言うひともいた。もっと他のことを言うひともいた。
「夫が、戦争に行ってしまって。都にいては危ないから、この町で待っていてと。そう言われたのですよ」
ついに誰かが尋ねた下世話な話に、先生は、明るく笑って、そう答えたらしい。
「とても心配症なひとなんです。若いころに仕事で訪れたこの町が、とてもよいところだったのだと、何度も何度も聞かされていました。本当によい町ですね。みなさま、よそものの私に、とても親切にしていただいて――」
そう言われれば、あることないことを噂していた誰も彼も、気まずくなってしまって、先生のまわりに空けていた隙間に、代わりに、あれもこれもと、気づかいとやさしさを詰めこみはじめた。
あのおんなはとなりの国の貴族だ、今もまだ逃げ回っているあの国の王子の愛人に違いない、戦争していた相手の国に隠せば、ばれないと思ったのだろう、すきを見て迎えにくるつもりなんだ、わたしたちは皆殺しにされてしまうよ。なんて、物語のようなつくり話をあちこちにしゃべっていたパン屋のおばさんが、買い物に行った先生に、ときどき、小さな焼き菓子をおまけして、”旦那さん、早く迎えにくるといいわねえ”なんて言っているのは、なんだかおかしかった。
先生は、家の戸口に小さな看板をかけた。”もじを、おしえます”。そして、ペンと巻物の絵。
トーマには、文字をまなぶことの意味があまりわからなかった。裕福なひとたちは、紙に蛇のような模様を書いて、それで言いたいことを伝えあうのだという。直接、会いにいけばいいのに。それが無理なら誰かが伝言をすればいいのに。
と、母親に言ったら、殴られた。トーマの母親も父親も、文字なんてまともに読めないというのに。”手伝いもしないで、そんな馬鹿なことを言っているひまがあるのなら”と、ひきずられて、はじめて先生の家の門をくぐったのは、冬のはじめのことだった。
なんてきれいなひとだろうと、思わず、口さえぽかんと開けて見とれてしまったことを覚えている。すっと伸ばされた背筋と、ふかい湖のような眼差しに、なんだかとてもどきどきしたのだ。あのときの、かざりけのない亜麻のシャツと深い土色のショールのコントラストが、まぶたの裏に焼きついている。
「お名前は」
先生は口をひらいた。理知的に低く響く、やさしくおちついた声で、低音が、ほんの少しだけざらざらとかすれていた。
「……トーマ」
どうしてか、どもりそうになった。母親が呆れて背中を叩いてきた。
先生はふわりと笑った。
「よろしくお願いします。私は」
右のてのひらを差し出された。シャツは少し大きいようで、手首まで裾がかぶっていた。
トーマはほとんどおそるおそる握りかえした。
「フェイといいます。今日からあなたの先生ですね」
それから一冬、三日おきに、トーマは先生の家に通ったのだ。しばらくは、扉の前に立つたびにどきどきして、少しでも背を大きく見せようと、肩を緊張させていた。先生はトーマの姿を見て、決まって「こんにちは」と微笑んで迎え入れてくれた。
冬が深まるころには、今度は、毛糸のマフラーの下で、寒さと雪の冷たさに肩を緊張させて、戸口に立った。先生は「こんにちは」と微笑んで、白いカップをトーマの前に置いてくれた。中には、いつもは温かいミルクがなみなみと入っていた。時々、トマトの味がする、野菜がごろごろ入ったスープのこともあった。
「野菜、大きい」
トーマがスプーンの上のにんじんを見ながら言うと、
「実は、料理がにがてなんです」
と、古傷だらけの両手を見せてくれた。
日常的にペンを使って文字を書くようになると、指やてのひらの皮が硬くなって、たこができるのだという。握手をした時の、意外とやわらかくなかった感触を思い出して、それから、きっと包丁でついたのだろうたくさんの古い傷を眺めて、トーマは呆れた声で言ったものだった。
「先生って、おんなっぽくないよね」
「だからこそ添い遂げられるおとこもいるのですよ。さあ、お勉強をはじめましょう、トーマさん」
先生は流暢にはなしをしたし、文字もとてもきれいだった。トーマのことを、まるで、おとなに対するように、トーマさんと呼ぶのが、耳にくすぐったく、嬉しかった。
いいですか、トーマさん。いくつかの単語は、文字にする時だけ、はなし言葉とは違う性別を持つことがあるのです。たとえば、”月”は男性、”書物”も男性、”国”は女性、”馬車”も女性になります。
他にも何人か、生徒はいた。ほとんどはトーマのような子供で、ちらほらとおとなもいた。
話を聞きつけたのか、雪のなか、違う町からわざわざ通う、物好きな人までいた。
そのみんなにも、トーマにするのとおなじようにトマトのスープを渡しているのかと思うと、胸の奥がじりじりすることもあった。
先生は教えるのが上手だった。大きな文字とかわいい絵でつづられた物語は、先生が、トーマのために書いてくれたのだという。しあわせの鳥を追いかけて不思議な旅をする兄弟のお話。トーマはそれを借りて帰って、たどたどしい声で、妹に読み聞かせてやった。
”しあわせの青い鳥は、本当は、最初から、ぼくたちの家に”。
妹はだいたい途中で眠ってしまうから、そこまでを声に出して読んだことはなかった。
トーマはどんどん文字を覚えた。先生は、トーマが物語をすらすら読めるようになるたびに、あたらしい物語を書いてくれた。授業が終わった後、すぐに帰らず、先生がペンを持つ姿を、頬杖をついて眺めていることもあった。傷だらけでごつごつした、だけれども細い先生の指。ペン先から紙を滑るインクの軌跡は、魔法のようにトーマをどきどきさせた。
誤魔化すように、尋ねた。
「先生は、どうして文字を覚えようなんて思ったの。そんなにてのひらが硬くなったら、やっぱり、おんなっぽくないよ」
すると先生は微笑んで、テーブルのひきだしから封筒を取り出して、眩しそうに掲げた。
「私が愛するおとこは、鉄とおなじくらい、文字が好きだからです」
「のろけられた」
なんてことだ。
とてもとても愛おしそうに、破れた真っ赤な封蝋をなでる先生に、トーマは「見せつけないでよ」なんて言ってみた。先生は、子供のようにくすくす笑った。
そうして、一冬がすぎた。
国じゅうのあちこちの道に積もっていた雪がとけて、外と再びつながりはじめる春は、長い夢からめざめたような季節だ。商売をするひとだとか、他の町にいるひとに会いにいくひとだとかがアラインズベルにやってきて、去っていく。
早摘みのキャベツやアスパラガス、いろとりどりの亜麻や木綿の布地、きらきらとした銅のお鍋やおたまと一緒に、終わったはずの戦争のはなしがやってきた。
となりの国の王様は死んで、となりの国は、なくなった。ずっと行方不明になっていたとなりの国の王子様が捕まって、いまは都の牢屋にいる。助けだすために、彼を慕うひとびとが戦っている。彼らは雪にうもれた森や山に隠れていて、なかなか居場所がわからない。トーマたちの王様は、道の雪がとけたその日、軍隊を連れて、彼らを倒しに行ったそうだ。
先生の旦那さんは、まだ先生を迎えにこなかった。先生はトーマを迎え入れるために扉を開けるとき、まるでついでのようにさりげなく、ポストの蓋を開けて、そして閉じるようになった。
だから、いつか、言われると思っていた。
こきょうへ、かえることにしました。
「どうして」なんて、とてもばかばかしい言葉に違いなかった。
先生は首をかしげて少しだけ考えこむような顔をした。それから言った。
「私が愛するおとこを、迎えにゆくのです」
それは、つまり、先生の旦那さんは。
先生はテーブルの向こうからトーマの目を見て微笑んだ。いつもとおなじ、ふんわりとした笑顔だった。湖のようにおだやかな眸の奥は、決意と絶望、そしてきっと喜びに色づいていた。あまりにも静かな水面。ふかいふかい水底を荒れ狂う激情。
「でも」
黙ったままでいたら、きっと言葉をうしなってしまう。トーマは首を横に振った。
先生は、その日ずいぶんと久しぶりに届いた封筒を取り出して、それを見下ろした。封は切られていた。トーマに授業をする前に目を通して、その後ずっとポケットに入れられていたせいで、封筒は少ししわになっていた。トーマはその中に書かれていることを想像した。
文字を扱うことができれば、遠くのひとに言葉を伝えることができる。
もしも先生が文字なんか読めなかったら、もしもこんな封筒なんか届かなかったら。このひとが、こんな泣きそうな顔をすることはなかった。
先生は封筒を置いて、左手の薬指から指輪をはずした。
ことん。と、テーブルが小さな音を立てた。何の飾りもない銀が、日差しにつややかにきらめいた。
先生が手を傷だらけにしても料理を食べさせたいひとはもういないのだと思うと、トーマはひどく悲しくなった。
「先生」
トーマは言った。
「何でしょうか、トーマさん」
先生はまだ微笑んでいた。いつもとおなじように。湖の底に、炎を抱えたままで。
「ずっとここにいれば、いいのに」
答えはわかっていた。
先生は傷だらけの両手の左右の指を互いに絡めて、しばらくその感触を確かめるように黙った後、口を開いた。
「ありがとう、だけど私は帰ります。添い遂げると誓ったおとこが、先に待っている」
その翌日、先生はいなくなっていた。
”トーマさんへ”とテーブルの上に残されていたのは手紙でも何でもなく勉強のための新しい物語で、それは他の生徒の分も、丁寧にまとめてとなりに並べられていた。
本格的に春がきて、夏がきて、秋がきた。遠くで戦争は続いていた。
また町が冬に眠り、そしてふたたび目覚めたときに、ようやく、聞いた。冬の間にとなりの国の元王子様は処刑され、彼を助け出そうとしていたひとびともみな倒されて、今度こそ戦争は終わったのだと。
どうしてあと一年はやく終わらなかったのだろうと、トーマは思った。
あの日、先生を迎えにきたのが、あんな残酷な封筒じゃなくて、先生が愛するおとこだったらよかったのに。
何年が経っても、時々、あのおだやかな笑顔とやさしい声、物語を紡ぐペン先のうつくしさを思い出す。