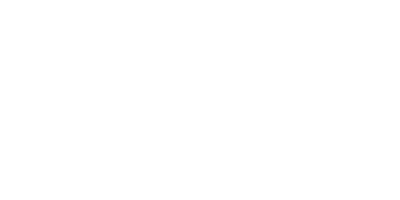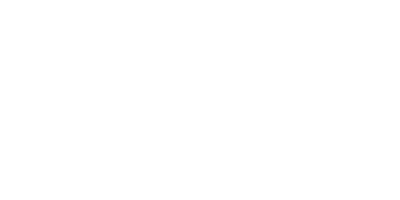僕の主人は変わり者だ。
いわゆる小国の王子というやつで、つまりはやんごとなきお方なのだが、残念ながらその順位は八番目。王座などまた夢の夢、長男以下のもういい歳した時期王候補からは歯牙にもかけられず、かといって、末であり庶子であり、あまりに不遇な生まれのために割と本気で王位簒奪を狙う二十番目の王子の視界にも入っていない、そういう中途半端な立場のお方だ。
熾烈な兄弟争いの中で育った僕からすれば、ちょっと生まれたのが早いからって当たり前のように偉ぶっているおっさんたちなど、その気になればいつでも引きずり落とせるのではないかと思うが、どうやら主人は違うらしい。
天気の良い日の午後、郊外の屋敷に今日もひきこもる主人とのどうでもいいような会話の中、ふとした拍子に、訊ねてしまった。
「あなたは、いつまでもここにいるつもりなのですか」
「ここほど居心地のよい場所はなかなかないと思うよ、きみ」
「そんなんだから、中途半端な王子だなんて言われるのですよ。野心の一つもお持ちにならないのですか」
中途半端なんて実際に言っているのは僕だけだ。と思っていたのだが、三月前、王城の舞踏会で、若い貴族が主人を指して中途半端とそものずばりを言っているのを聞いてしまった。まったくその通りだと思ったが、少しばかり悔しいとも思ってしまった。不覚なことだ。
「野心か」
主人は薄く笑った。
「野心です」
「たとえば、年上の兄たちを鏖にして、王座に座ることだとか」
「…………」
「きみね。そんなことをしてみなさい。たとえば、長兄様の晩餐の盃に、あり得ないことだが、うまいこと毒を入れたとしよう。その毒が、銀杯を黒く濁らせず、自称美食家のあの男の無駄に敏感な舌を欺けるほど、味もにおいもなかったとして。そして。私がやったという証拠など何一つなかったとして!」
ゆるゆると主人は語る。猫のような金色の眸を気怠げに細め、東国の商人から贈られた扇子で、音もなく微風を浴びながら。
「証拠など、何一つなかったとして」
僕は訊ねた。
主人はくくと笑った。扇子の風に揺れる黒髪は、まったく陰気であった。どころか、肌は地黒だというのに青白く、頬の肉は削げており、まったく、まったく、陰気であった。病などない。普段からこうなのだ。
「なかったとして。それでも、その夜のうちに衛兵がこの屋敷を取り囲み、抵抗の末に私は討ち取られるだろう。もちろん、きみもだ。王の血とはそういうものなのだよ、きみ!」
僕は主人のまことにひょろりとした手首を眺めながら訊ねた。
「あなたが抵抗なさるのですか」
「さあ、どうだろうね、どうだろう。気分次第さ。けれどおなじことだ。その夜たとえ何が起ころうと、逆賊は抵抗の末に討ち取られるのさ。王の血とはそういうものなのだよ、謀略とは、政治とは! わかるかい、ねえ、きみ」
「はあ」
僕は曖昧に頷いた。
主人はますます楽しそうだった。ぱたん、と扇子を閉じてその端を指先で撫で回し、それから僕を近くに呼んで、扇子の先でぺしぺしと頭を叩いてきた。大して痛くなかったし、この人の行動が意味不明なのはいつものことなので、僕は気にしないことにした。
「しかし、だれが、空気のような八番目の王子を殺して得をするのでしょうか」
主人は少し気に入らなさそうに金色の双眸を細めた。質問が勘に触ったのかも知れないし、扇子を無視されたことがつまらなかったのかも知れない。
「きみねえ。王家にはいろいろあるのだよ。わたしは確かに王にはなれないけれど、あの舌の腐った男をはじめ、他の兄弟が欲しがるようなものを、いくつかは持っている。たとえば、きみにあげたあれだ。健脚な母が空島を探しに出かけるにあたって置き残していった首飾りは、王城の地下に眠る古代の装置を動かすための鍵であるし」
「そうは見えませんでしたが」
「嘘だからな」
「……そうですよね」
そんな大事なものを、くれてやろうと無造作に放り投げてくるはずもない。
実際、売れないかと見たところ、残念ながら宝石は硝子玉で、台座は鍍金だった。街の市場で売っているような、親に小遣いをもらっている餓鬼がはじめての恋人に買ってやるような、そういう品だ。
「あれは、街の市場で買ってきたのだ。街は広いし、ものが溢れている。どこへ行ってよいものか、何を買えばよいものか、とんと見当もつかぬ」
「僕が知らない間に抜けだしたのですか。普段は屋敷から一歩も外へ出ないというのに」
「きみが里帰りなどしていなければ連れて出たものを。きみは街に詳しいのだから」
主人は不機嫌そうに言った。
「ところで、あれはどうしたね」
「あれとは」
主人はため息をついた。
「首飾りだ」
僕は記憶を辿るように視線を逸らした。
「妹にやりました。ああいう玩具が好きな歳の」
「…………そうか」
主人はわずかに眉間に皺を寄せ、僕の頭を扇子で強く叩いた。
さすがに片手で頭をかばって、離れる。
「何をするのですか」
「主人の気遣いもわからぬのかね、きみは。呆れたものだ」
「気遣いで頭を叩くのですか」
主人は扇子を横目にし、自分の逆の手のひらを叩いた。ぱし、と、乾いた音が響いた。
「きみに似合うと思ったのだが」
「とんでもない」
僕は主人を睨んだ。
主人は金色の眸で僕を見返してきた。
「王冠を飾る類の価値はないが、綺麗に輝くあの数珠玉と硝子は、きみに似合うと思ったのだが。ねえ、きみ。男兄弟の間で育ったのはわかるけれど、もう少し、女の子らしい格好をしてみてもよいのではないかね」
「……余計なお世話です。僕は今のままで満足しています」
「せめて、”わたくし”と」
「とんでもない!」
思わず叫び返してしまった。
主人は深く深くため息をついて、頬杖をついた。屋敷の窓から外を眺め、長い長い沈黙のあと、また、ため息をついた。
外には午後の光が輝いている。
「……何か、仰りたいことがあれば」
「何一つ。何一つとしてあるものかね。わたしは今、わたしが持つうらやむべき宝の一つを、他の兄弟達にはまだまだ内緒にしておこうと誓っているところだというのに。さあ、わたしの有能な従者よ、お茶を入れ、焼き菓子を持ってきてくれたまえ。この小さな屋敷にひきこもるばかりの、八番目の中途半端な王子の、毎日の一番の楽しみなのだからね」
「…………かしこまりました」
僕は一礼して主人の前を辞した。
僕の主人は変わり者だ。いわゆる小国の王子というやつだが、中途半端な八番目で、将来性はない。しかも、陰気で、ひきこもりだ。
けれど、口下手さを流暢な悪態でごまかす、とても優しい人だ。
僕は扉を締めて、服の胸元の生地越しに首飾りに触れてから、お茶の準備をするべく歩き出した。