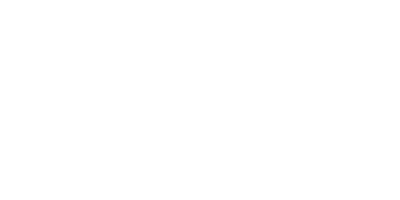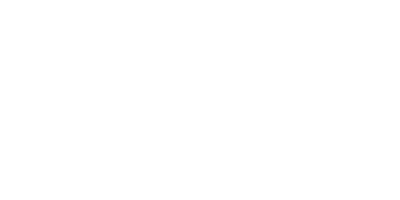今日も空は青い。きっと明日も青いし、明後日も青いのだろう。
サキが知るかぎり、ラウンドテーブルシティに雨が降ったことはない。曇りも、雪もない。
天候の変化は次に実装されるはずだったアップデートに含まれていた。
サキは今更そんな演出でサーバを重くすることなんてないのにと表面上は鼻で笑いながら、雨が降ったら久しぶりに首都を離れて、アイテム生成の素材になる鉱石でも探しながら、一通りマップを歩きまわってみようと密かに決めていた。
クラウドカッコーアイランド・オンラインはサービス開始から二年になる地味なネットゲームで、よくあるファンタジーランドでの剣と魔法の大冒険と、石造りの都市での商売と生産の生活を疑似体験できるという、やっぱりよくある趣旨のものだった。
システムだって他のゲームと似たようなものだ。
目新しいといえば、パソコンではなく頭に付けるゴーグルのようなW3DGというハードを使ってゲーム世界に接続するということくらいだ。
しかし、W3DGの発売と同時に発表されたファンタジーの注目タイトルは他にあったから流行りもの好きはそちらを選んだし、コアなゲーマーはこぞって開発されたFPSの方に群がったので、クラウドカッコーアイランド・オンラインは、サービス開始以来、なんとなくあか抜けない、過疎寸前の、まあ、言い方をすれば、まったりとした雰囲気で、知る人ぞ知るマイナーゲーという地位を保ち続けている。
見上げた空は、ただ青い。最新の(といっても二年前の、だが)技術には、ただただ感心するばかりだ。
澄み渡る蒼穹。その遙か彼方には、神の国がある。神はかつて地上の危機に、カッコーの翼を持つ乙女を遣わし、英雄に剣を授けた。だから神の国はクラウドカッコーランドと呼ばれている。何故サービス名ではアイランドなのかは、誰も知らない。なぜなら誰も、未だ、神の国には辿り着いたことがないからだ。
そして、クラウドカッコーアイランド・オンラインのプレイヤー達にとって、空は、別の意味でも特別な場所だった。
――半年前、空にメッセージが表示された。
“剣を握り、我が門を目指せ。”
その日、世界中のW3DGが一斉に誤作動を起こしたらしい。
ハッキングだという噂も流れ、テロだと大騒ぎになった。
とにかく、W3DGでゲームを楽しんでいた莫大な数のプレイヤーがログアウトできなくなり、架空の世界に繋ぎ止められた。
一週間くらいは公式の掲示板で外と情報交換をすることができたけれど、それも唐突にぷつりと途絶えた。
人為的な事件であるということしかわからなかった。
サキはまわりの騒ぎを聞きながら、ぼんやりと、自分が遊んでいたのがFPSやホラーゲームでなくてよかった、と思った。あちらのゲーム世界は地獄だろうと。
ラウンドテーブルシティはほとんど一ヶ月、混乱に掻き回された。けれどもプレイヤーも慣れてきたのか、落ち着いて救助を纏うとか、長期休みだと思ってこの気にゲームを楽しもうとか、神の門ってクラウドカッコーランドなんじゃないの攻略してみるかとか、それぞれに徒党を組んだりソロだったりで、なんとなく活動を始めた。
サキも、この世界での日常に戻ることにした。つまり、ラウンドテーブルシティの、武器鍛冶に。
ハンドサインでコマンドを呼び出し、ショートカットから武器生成スキルを選択。素材となる鉱石やその他のアイテムをスロットに収め、表示された金槌マークをタイミングよく押す。
やがて、ピロリロリリリンという景気のいい鈴の音とともに完成した武器がアイテムスロットに追加されるので、サキは出来たばかりのロングソードを装備して、性能を確かめて、更にはグラフィックに惚れ惚れとする。
澄み渡った空を映す鋼。一体どれだけのパターンのグラフィックが登録されているのか、同じものは二度と打てない。性能さえ、本来はランダムだ。
サキは独自に素材の組み合わせやスキルのタイミング、その他いろいろな条件を調べ上げて、性能や見た目の方向性を操れるようになってきていた。
客が望む、正しくそのものを。それが鍛冶師としてのサキの売りで、信条だ。
まだムラはあるが、スキルレベルの向上に伴い安定しつつある。
こんなことをできる鍛冶師は、多くても、きっと他には一人や二人しかいない。
一人で剣を振って満足していると、注文主が近づいてきた。
完成時間ぴったりに引き取りにくるなんて、熱心な挑戦者だ。
知人の知人の紹介で受けた新しい客で、サキは彼のことをまだ詳しくは知らなかったが。
サキはにっこり微笑んで、その少年剣士に向かって手を出した。
「できてるよ。データ見る?」
剣の柄を握ったまま、刃先を彼に向ける。少年は一瞬、鼻白んだ表情を浮かべたが、この物騒な動作が装備データの共有コマンドだったことをすぐに思い出したらしく、そっと、刃の中程に指先を当てた。
サキは、少年が、ほう、と息を吐くのを誇らしい気分で聞いた。
「……なかなかじゃないか」
「でしょう? これで、お約束通りの二十二万えん! 頼んでよかったでしょう?」
「円って言うなよ……」
少年剣士は、跳ねた栗毛をがりがりと掻いた。
サキは言い返した。
「交換ウィンドウで金額を見せてくれれば、単位を思い出せるかもね」
「っ! この守銭奴!」俺たちが何のために――と言いかけただろう言葉を、少年は、危ないところで飲み込んだ。
サキは笑顔でその様子を眺めていた。“挑戦者“と呼ばれる、神の門に挑むプレイヤーたち。彼らは確かにサキたちの救い主になるのかも知れない。けれど時に横暴で、自分たち以外のプレイヤーを見下している面がある。
「……サービス価格だと思うけど?」サキは言った。「素材を買うお金がなければ、この剣の耐久度がなくなる頃、新しいのを作ってあげられない」
「わかってるよ、悪かった」
少年剣士はアイテム交換申請をしてきた。サキの視界の隅で、通知シグナルがちかちかと光る。
サキは気づかないふりをして言った。
「こんなことで怒るなんて。普段、よっぽど怒鳴り散らしてるってこと?」
「違う!」
少年は言った。サキは彼を見上げた。まるで一昔前のRPGの主人公のような少年。意志の強そうな眉。黒く輝く眸。引き結ばれた唇。
子供の頃からディスプレイ越しに見知っていた偶像が目の前にいるような感覚になって、サキは一瞬、馬鹿なことを思った。
“まるでゲームみたい”。
「円って言われると、現実を思い出すだろ。二十万もあったら、何ができるだろうな」
「あ、ああ……」サキは思わず頷いた。「ごめん。そうだね。二十二万ベリル」
アイテム交換申請を承諾。交換ウィンドウに作ったばかりのロングソードと、おまけの回復アイテムを置いて、確定コマンド。少年は取引金額を入力後、一呼吸の間の後で確定コマンド。サキは、おまけをつけられた客はいつも取引に変な間があくなあと思いながら、最後に交換コマンドを選択した。
これで、ロングソードは少年の元へ。二十二万ベリルはサキの所持金へ。本物の緑柱石[ベリル]よりずっと鮮やかな青緑色の光が視界の右上で踊る。
少年は剣を装備して確かめて、「ものはいいのに」と呟いた。
「他に、何が不満?」
「無属性ロングソードに二十二万は法外だと思うけど」
「他の鍛冶師におなじ注文をしたら、十本打たせても、希望のものはできないと思うよ」
この半年で、武具鍛冶は激増した。嗜好品や衣装をつくっていた生産系プレイヤーが、一斉に、この世界でサバイバルをするための実用品や食料品の生産に乗り換えたのだ。
特に、武具は人気だった。挑戦者はもちろん、素材発掘プレイヤーや、行商プレイヤーだって買う。アイテムそれぞれに耐久値が設定しているために買ったらそれきりとはならず、いつても需要はある。
「最近は、腕が悪いの増えたから」
生き残るために職種を転向したところで、既に先達からは出遅れている。
情報サイトに繋げられないから、素材の組み合わせ方もろくにわからない。鉱石の発掘ポイントだって生聞きだから揃えられない。そして昔からの生産職プレイヤーは、決して、その秘密を喋らない。
「あっちの通りの薬屋もおなじこと言ってたぞ」
「アイシャ? 彼女はすごいよ。素材ほとんど自分で狩って来る強者だし」
「そうなのか!?」
「うん。でも薬草師は戦闘中の回復スキルないからPTには向かないよ。誘うなら素直に僧侶にしときなよ」
「ああ……」少年は、納得できていなさそうな様子で頷いた。
サキは肩を竦めた。
「さて、そろそろ仕事の邪魔だ」
「忙しいのか?」
「ううん、まったく」
「何なんだよ……」
「仕事が趣味なんだよ。頼まれなくてもつくるんだ」
「在庫づくりか?」
「そう」
サキは頷いた。生産系プレイヤーの得点である大きなアイテムインベントリの奥から、剣を取り出す。
装備ではなく、所持で、グラフィックを見せる。
「これはエルツが欲しがってた天使特攻バスタードソード」
「……天使特攻なんてあったのか」
「で、これが、ヘイゼルに売る予定のオーガアックス」
「ごっつい……」
「こっちはゆっきー用の闇属性ゲイボーグ」
「加護武器じゃねえか! つくれるのか、それ!?」
「いちいちうるさいなあ、腕がいいんだってば。特殊アイテム必要で面倒臭かったけど。多少珍しいものくらいだったら、予約しといてくれれば次までにつくっといてあげる」
「…………考えとく」
「わかった」
サキは武器をインベントリにしまった。
「で、でも、そのゲイボーグ、ちょっとだけ貸してくれないか……」
「嫌だよ」
加護武器というのは、ようするに、妖精やら神やら悪魔やらの加護が宿っているという設定の武器で、素材集めからして気が遠くなるような話だし、製造も難しい。更には装備条件も厳しい。その代わりに、冗談みたいな威力を持っている。公式チート、とはよく言ったものだ。
サーバに数本しかない加護武器を握ってみたいのはわかる。けれど、持ち逃げされたんじゃたまったものではない。今は借りるだけのつもりだとしても、強い武器は人を変える。ゲームだったらまだいいけど、ゲームだけれど、ここでは、だめだ。サキは装備できないから普通に持っていられるだけで。
売ったらいくらの値がつくだろうと、思うこともある。そうした方がいいのかも知れない。皆のためには。
「ゆっきーが」サキは言った。「戻ってきたら、渡すんだ」
「誰だよ、知り合いか……」少年は僅かに顔を強ばらせた。「……雪見酒?」
雪見酒。ちょっとふざけた名前の最高レベル挑戦者。早くから神の門攻略に乗り出し、二ヶ月前に行方不明になった。
この世界で死んだ者がどうなるのか、誰も知らない。ある者は復活地点に戻ってくるし、ある者は二度と現れない。復活座標が狂って密林の奥に飛ばされていたよと笑いながら帰ってきた者だっている。彼らの運命がどう分かれたのか、誰も知らない。だからまだ望みはある。
「そう」サキは頷いた。「だからあげない。ゆっきーがこれを装備したら、きっと、神だって倒せる。後は、門を開けてゲームクリア。でしょう?」
「…………」
少年は沈黙して、逃れるように空を見上げた。昨日も今日も明日も明後日も空は青い。もう記憶に薄い日本の空よりずっと鮮やかな、洗練されたグラフィック。鳥の影もなければ、吹き抜ける風の音もしない、ラウンドテーブルシティの空。
昔、サキはこの空が好きで、見上げた青に成功を祈り武器を打っていた。
今、サキはこの空が嫌いで、切先が届くことを祈って武器を打っている。
「そうだな」
少年は言った。苦い声だ、とサキは思った。
「だけど」少年は言葉を詰まらせて。やがて、吐息と共に吐き出した。「俺が」
「何さ」
「俺が――雪見酒より強くなったら、それをくれ」
「は?」
「も、もしもの話でいい。同レベルになったら、先に取りに来た方がもらう。いや、貨を払ってもいい。レベルがカンストする頃には、ベリルなんか、いくらでもあるはずだからな」
サキは半ば呆気に取られて、少年を眺めた。ただ軽口を叩いて目の前を通り過ぎるはずだった客の一人であった彼に、はじめて認識カーソルを合わす。
“シトゥイーク 剣士 lv.53”
「……弱っ」
「はっ!?」
「いや何でもない。それよりきみ、名前呼びにくいってよく言われない?」
さっき交換ウィンドウを開いたときは気付かなかった。
「うるせえ! っていうか、話を逸らすな! 条件を満たしたら、売ってくれってば!」
――それを売ってくれと言ってきた客が今までにいなかったわけではなかったが。
サキは考えた。今からこいつが頑張って、レベルカンストまでは随分かかる。なにせ、レベル76以降の経験値テーブルは、マゾ仕様と評判高い。諦めるにはいい頃合いになる、のかも知れない。高レベルの挑戦者に何度も目をつけられてきて、うんざりしていたし。先約ができたと言ってしまえば、楽になるかも知れない。
「……いいけど」
「えっ!」少年は表情を輝かせた。よくできたゲームだ、とサキは思った。思って、少し虚しくなった。
「いいけど、槍スキル持ってるの?」
「これから取るんだよ。スキルに合わせて武器を選ぶのは序盤で、レア武器に合わせてスキルを取るのが終盤だ」
「まあーそのへんは人それぞれだけど、賢くはないよ。後でポイント足りなくて泣くよ? スキルリセット高いよ? 一財産どころじゃないよ?」
「し、知ってる」
少年は目を泳がせた。サキはため息をついた。
「まあ、頑張っておいで。その剣が壊れたら、新しいのを打ってあげる。属性結晶を持ってきてくれれば付与もしてあげるよ」
「付与術も使えるのか?」
「サポートNPC。レベル高いよ」
「そりゃ頼もしい」
少年は納得した様子で頷いた。
それから、彼は「あっ!」と声を上げた。「悪い、待ち合わせの時間過ぎてる! またな!」
「え? ああ、うん。またね」
サキは思わずぽかんとして頷いた。
遠ざかる背に、なんとなく手を振ってみる。
再会があればいいのだが。
サキは遠ざかる後ろ姿を見送りながら、あの一振りの剣が彼を守りますようにと祈った。
すべてを見下ろして、ラウンドテーブルシティの空は青い。
いつか誰かの刃が偽りを破る日まで。