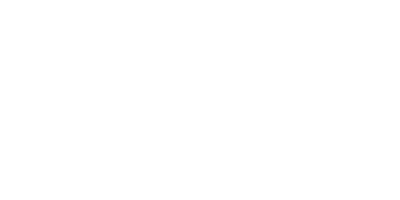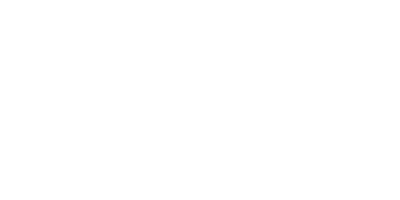晩秋の吹雪に襲われ、白く閉ざされた群島地域でのことだ。
厚い厚い雲の向こうで日も落ちて、長い夜がやってくる。肌を切る寒さと深い闇を逃れた船人は、手近な店に転がり込んで、熱気に身を寄せあい、他者と酒を飲み交わす。
彼らのことなど意に介さぬとばかりに天から吹き降ろすその雪は、秋と共に、かもめの姿を押し流すために、”かもめ流し”と呼ばれている。
囁かれる悪態の間を縫うように、一人の男が口を開いた。
奇妙な風体の彼は言う。憂鬱な雪の日を、無為に過ごさなければならぬのならば、どうせなら、俺の話につきあってくれないか。
幾つかの遺物と噂以外は謎に埋もれた西の大陸。その失われた記憶と歴史を、今宵、ここに集ったかもめたちの手で、蘇らせてみようじゃないか。
と。ゆるりと笑んで、彼は誘うように片手をかざす。
「よければ俺に、その物語を聞かせてくれないか」
――これは、彼の言葉に応えて吹雪の夜に語られた、多くの物語の一つ。
虹を追う少女と冒険者の物語。
◆
男はカウンターの止まり木で脚を組み、少しのあいだ思案してから、口を開いた。
「雪は未だに降り止まず、外はいよいよ白く塗り潰されようとしている――この夜に、語るにふさわしい話とは何だろう?
残念ながら、僕は考古学は門外漢だ。だから、ささやかな物語を話そう。ある若き考古学者と虹のかなたを歌う歌についてだ」
◆
まず、僕が何者かを説明する必要がある。
きみたちは、冒険者という人種を知っているだろうか? そう、その名の通り、冒険を信条とする者のことだ。
誰も行ったことがないところへ行き、誰も為したことがないことを為すことを目的とする者。それぞれが胸に抱く熱情のため、地図に残る白紙に、いにしえの遺跡の闇に、遥か虹のかなたに、困難に挑む者のことだ。
悲しいことに、小銭でちんけな小鬼や獣を追いかけ回したり、商隊の護衛で街道を往復し続けることに血道を上げている、日雇いの何でも屋かゴロツキだと思われることが多いけれども――まあ、実際、そういう連中が少なくないから仕方がない。職業を聞いて「冒険者」と応える奴は、十中八九、その日暮らしの何でも屋のゴロツキだ。
だって、ねえ、仕事にできるほど日常的で確実な、そこに何の未知と困難が、冒険がある?
さて。僕には、冒険の種を持ち込んでくれる、得がたくも厄介な友人たちがいる。今回お話する考古学者もその一人だ。
彼女は探索に人生を捧げる種類の人間で、度々、僕の元を訪れては、古びた硬貨だの、得体のしれない牙や羽だの、曰くつきの指輪だのを並べて、その正体と来し方を探る旅に僕を誘った。
その日もそうだった。五十年に一度、大陸の西の涯の谷にかかる虹の伝承を携えて。
その日。あれは夏の終わりだった。
けれど少しの脚色は許してくれ。語り手とは物語の中では神にも匹敵するものだ。
だからこの話は冬から始まる。雪に閉ざされた群島地域。足止めされたかもめたちの熱気に満ち、赤々と灯る暖炉で照らされた宿の扉の前に、彼女が立つところから。
◆
雪でますます重くなった扉を、勢いをつけて開け放つと、灯火と熱気が溢れ出てきた。
わたしは想像以上の盛況さに驚いて立ち尽くし、それから、寒いじゃねえかと怒鳴られて、慌てて駆け込み、扉を閉めた。
旅の間にすっかり擦り切れてしまったコートを叩く。重い雪がぽとぽと床に落ち、溶けて水たまりになっていく。外にいる間に冷え切っていた指先や耳がちりちりする。
客に麦酒を運んでいた娘が、少しの呆れを含んだ笑顔で「いらっしゃい」と言った。「こんな遅くまで外にいたの? あーあ、すっかり冷えちゃって。ほら、そっちの奥、暖炉の方に行きなさい」
わたしはうなずいて、店内を見渡した。
そして、暖炉から少し離れたカウンターのとまり木に探し人の姿を見つけると、大声で呼びかけながら、早足で近づいていった。この男は目を離すとすぐいなくなって帰ってこない。今だって待ち合わせ場所に一向に来ないものだから、この酷い雪の中、通りの端から順番に店を訪ねなければならなかった。
「ねえ、ちょっと、サリスさん、夕方には馬車で出発するって言いましたよね! どうしてこんなところでくつろいでるんですか!」
「やあ、シルヴィ」
冒険者はゆるゆると笑った。何も悪いと思っていなさそうな態度が腹立たしい。
わたしは、待ち合わせをすっぽかした理由を問いただそうと口を開きかけ、周囲の様子に気づいて、ぎょっとした。
店いっぱいの、人、人、人。水夫であったり、旅人風であったりする者が多い。彼らの多くが、こちらを見て、呆気にとられたような顔をしていた。
男はガラスの杯でミードを飲みながら、わたしを見下ろした。愉快そうな薄笑いが嫌味ったらしい。足でも踏んでやろうか。しかし冒険者は長い足を優雅に組んで、とまり木の足置きに引っかけているから届かない。
「たわむれの途中だったんだ。どうせ今夜はこの島からは出られない。だから雪がやむまで順番に物語りでもしようって。今、僕の番。話し始めた途端にきみが乱入してきたんだよ」
なんだそれは……。呆れと怒りで咄嗟に声が出なかった。
わたしが雪の中をさまよっている間に、呑気にも、与太話を肴に酒浸りになるつもりだったのか。わたしは怒鳴りつけようと息を吸い込んで、周りの注目に気がついて、なんとか言葉を飲み込んだ。
この雪だ。確かに外に出たくはないだろう。けれど――
「急いで出発しないと間に合わないって、わたし、言いましたよね。大陸の西の涯の谷に魔法の虹がかかるのは五十年に一度だけって」
「あの歌か」
どうだったかな、とでも、とぼけられると思ったが、冒険者は、ふと真面目な表情になった。少し低く、ざらざらして、けれども通りのよい声は、ただ一言であるのに、店内に染みるように響いて聞こえた。彼の手の中では、灯火の光を受けたミードが、ガラスの中で黄金の炎のように輝いていた。
「その辺境の涯の魔法の虹を追いかければ、今度こそ本当に、あの歌のように辿り着けるのかな? きみの求める、虹のかなたの国へ」
「それは」
そうだ、とはすぐには頷けなかった。
わたしはこれまで何度も、黴だらけの古文書や擦り切れた石碑、信用ならない伝承や、由来の知れない品々を抱えて、この冒険者の元を訪れた。目の前にそうしたものを転がして、それらが示すどこへ行きたいのだと告げれば、彼は、しかつめらしく旅路や秘境の危険を散々に脅かした最後には、「高くつくよ」とため息をついて了承してくれるのだ。
彼は、どこで手に入れたのか想像もつかない、古い地図をテーブルに広げて、「今いるのがここ」と言って一点を指し、それから、「目的地はここ」と、遠く離れた点を指し示す。それは険しい山脈であったり、大きな湖であったり、海を隔てた別大陸であったり、まだ誰も描いていない白紙の領域であったりした。
それを今更……と、思って、わたしは気がついた。彼は今、ここに集まって人々に物語りをしているのだ。そして、わたしに何かを話させようしている。約束を破って平然としているどころか、わたしまで酔っ払いの遊びに引きずり込もうとして。
わたしは彼を睨んだ。根拠なんて、彼も知っているはずだった。
「あるわけないでしょうそんなもの! 今までだってそうだったじゃないですか。今はもう忘れ去られたもの、失われたと思われているもの、実在さえも疑わしいものを探しに行くのに、根拠があったらおかしいでしょう」
言いながら、我ながら呆れた話だと思ったけれども。
冒険者は満足そうに目を細めた。そういう旅を好むのだと言ったのは彼だった。だから、わたしの探索にいつも付き合ってくれるのだと。互いの意志なんてとっくに知っている。旅路は危険で何度も死にかけたし、探すものが見つからないことも見当違いであることも珍しくなかった。それでも、わたしたちは行くのだ。だから、ほら。
彼はミードを飲み干してとまり木から立ち上がると、何枚かの硬貨をカウンターに置き、足元から革鞄を拾い上げ、芝居の主役のようによく通る声で、かもめたちに告げた。
「急用が入ったから失礼するよ。勇気ある少女は、ある民謡に見出した神秘を追って、ひとりの冒険者を道連れに、虹のかなたの国を目指して出発した、ということにしておいてくれ。何せ、今日ほどの出発日和は他にない。あたりは雪に閉ざされている。その向こうが見知った場所のままだと誰が断言できる? 閉ざされた夜にこそ、物語の最中にこそ、幻想と伝説は立ち現れる」
彼はわたしの頭を乱暴に撫でて、明るく暖かい店内を縦断していく。
わたしは呆気に取られながら追いかけた。
「格好つけも脈絡がないと決まりませんよ。結局、お話終わってないじゃないですか」
「帰ってきてもまだやってたら続きを話すよ」
「近所へ買い物に行くみたいに言わないでください」
軽口を言い合いながら、わたしたちは暖かな店内を後にして、猛吹雪の中、長らく出発を待っていた馬車に乗り込んだ。
◆
シルヴィと僕を乗せた馬車は、何日も何日もかけて、西へ西へと走り続けた。
それは以前の旅で手に入れた二頭立ての箱馬車で、長旅用の、なかなか頑丈なものだった。それを引く馬たちも、市場で見繕った、脚の太い立派な二頭だった。片方は栗毛、片方は葦毛で、どちらも日に当たると毛並みがつやつやと光ったものだ。
馬車は雪に埋もれた街道を進み、道から外れて更に進んだ。一向に晴れない空の下、昼と夜がぐるぐるとめぐった。
シルヴィは室内で本を読んだり、外を眺めたりして時間を潰していたが、じきに飽きて、寝転がってうつらうつらとしていることが多くなった。彼女は、荷物と彼女自身が入るだけの空間を残して持ち込んだ、大量の毛布とクッションに、巣の中の小鳥のようにぬくぬくと包まっていた。
僕はといえば、一日中、御者台で寒い思いをし続けていた。行く手は真っ白で何も見えないし、手袋をしていても指の感覚がなくなるし、あまりに静かなものだから眠くなるし――けれど、眠るわけにはいかなかった。
景色に紛れて忍び寄る雪狼の群、獰猛な猟犬を従えた夜の狩人、雪に埋もれた骸を探して徘徊う地底の獣……
時には迂廻して避け、時には隠れてやり過ごし、時には武力で追い払った。方角を失いかけては磁石と地図と曇天を睨んで正しい行く先を探した。気を抜ける時間はなかった。
特に、野宿の夜は酷いものだった。
限りなく黒に近い灰色の夜空には一片の星もなく、刻一刻と嵩を増していく一面の雪の中、まばらな木や岩の陰に馬車をとめて。光は遭難者の亡霊を呼び寄せるから、馬車の中に小さなガラス灯だけをつけて、暗闇の中で朝を待った。時々、危険がなさそうな夜には、僕はシルヴィと毛布とクッションを奥に押し込んで、馬車に入って暖を取れることもあった。
馬はずっと外にいたものだから、どんどん体温が下がっていき、旅が始まってしばらく経った頃には、最初は燃えるようだった血潮は完全に凍り付いてしまった。
それでも氷の馬は走り続けた。
更に昼と夜がぐるぐるとめぐるうち、地形の起伏が大きくなり、木々が増えてきて、ついに吹雪を抜けた。
空は抜けるように青く、その天辺で輝く太陽の熱が、すっかり冷たくなった体に染みこんで心地よかった。僕は馬車の小窓を叩いてから、久しぶりの空を見上げて伸びをした。
シルヴィが、御者台と繋がる窓を開けて歓声を上げ、それから次に悲鳴を上げた。
すっかり氷になった馬が、暑さに耐えられず、どろどろ溶けていくところだったからだ。
僕は慌てて馬車を停め、御者台から飛び降りた。完全に溶けてしまう前になんとか自由にしてやると、二頭の氷の馬は身をひるがえして、背後の吹雪の中に駆け戻っていった。きっと、氷の生き物は太陽の下では生きられないのだと、本能的に察したのだろう。
クッションを抱えて飛び出してきたシルヴィが、呆気にとられてそれを見送った。
そういうわけで、馬車は動かなくなった。
地図を見ると近くに宿場町があるはずだったから、最低限の荷物を馬車から持ち出して進むことにした。シルヴィは名残惜しそうに、時々振り返ってため息をついていた。
◆
「幸い、宿場町へは夕刻のうちに辿り着いた。
慌ただしく買い物をし、移動のための馬の手配を済ませ、ようやく宿で一息ついて、始まったばかりの旅の、更に先のことを話し合った」
男は一度、大きくため息をついて、ガラス杯の中のミードを舐めた。
「ここから先は、しばらくは退屈な話だ。
ひたすらに、草原と山と丘と荒野と砂漠とまた山を越えて、西へ西へと進むだけだから。
多少の危険や計算違いがなかったわけではないが、別に、いちいち数え上げていくほどのものでもない。
今の話と似たようなものだ。え? そもそも、雪の中を馬車で進めたのかって? もちろん進めるはずがない。しかし多少の困難や代償を許容できるなら、進めない道を進む方法なんていくらでもある――と、こんな弁明を、一々していくのは気乗りがしない。
だから、そうだな。旅の終わりが近づくまでは、少し話を脱線させて、そもそもの始まりについて語ろう」
◆
わたしは、遠い場所から来たの、と。
密林の奥深くで過ごした夜のこと。生い茂る木々を見上げながら、シルヴィは囁いた。
闇の底、噎せ返るような土と植物の匂いの中、二人の間で焚火が赤々と燃えていた。
彼女は外套に包まって膝を抱え、小さな声で続けた。
わたしは幼い頃、この世界の言葉では表わせない、今はもう奇妙に感じる場所にいたんです。そこには、天にも届きそうな四角い建物がたくさん並んでいて、地面は固く黒く塗り固められていました。わたしには、おとうさんとおかあさんがいて、白くて大きな建物の中に住んでいました。
僕は遠く響く一角獣の鳴き声に耳を澄ませながら、曖昧な相槌を打った。
初めて聞く話ではなかった。シルヴィは時々、かつて彼女がいた遠い場所の話をすることがあった。それは空をゆく鉄の鳥の話であったり、規則的に時を刻む機械のことであったり、聞き慣れぬ料理を囲んだ家族の団欒のことだったりした。
あれは、わたしが六つか七つのとき、ある雨の日のことでした、と、彼女は続けた。
僕は意識の片隅で、その景色を想像した。何度も聞いたものだから、すっかり憶えてしまっていた。
雨に濡らされた道は黒々と輝き、両端には雨粒を浴びて紫の花が咲き乱れる中を、水音を立てて白線を踏みながら、鮮やかな雨具を着た女の子がはしゃいで駆けていく。
彼女は軽やかに振り返り、おかあさん、と口を開きかけて、けれどその声が母親に届くことはなかった。
空から彼女に注いだ七色の光が、彼女と彼女の世界の間を、絶望的に隔ててしまったからだ。
――だから、わたしは、虹のかなたの国へゆく。わたしのいた場所へ帰るの。
目を閉じて、震える声で、冒険の度に彼女は繰り返す。そして、小さな声で歌をくちずさむ。誓いのように、祈りのように。
その世界では、ある吟遊詩人が広め、すっかり定着した民謡だった。
シルヴィの故郷では、ある少女の、魔法の旅の物語の歌なのだそうだ。
青い鳥が飛んでゆく、虹の向こうの夢の国。そこではどんな願いも叶う。
シルヴィは虹にかかわる伝承と伝説をあさり、何度も空振りを繰り返しながら、危険な旅を繰り返す。
◆
「シルヴィ、次はきみが話をする番だ」
と、冒険者が突然言い出した。脈絡がないのはいつものことだったが、今回はすぐには返事を出来なかった。わたしは、ごうごうと唸りを上げる風に吹き飛ばされないよう、岩場の影にうずくまって、ばさばさうるさいコートを抑えるのに精一杯だった。
草原と山と丘と荒野と砂漠とまた山を越え、険しい山脈の最後の山を降りる斜面から、眼下には、岩とまばらな草木に彩られて広がる平野と、その向こうの海が見えていた。平野には、北西から南西の海まで、古の巨人の神の剣で切り裂かれたような亀裂が走っている。
西の涯の、雄大な景色だ。だけど、感動するには風が強すぎる。
「何の話ですか」
冒険者は岩場の端から彼方を見下ろすのをやめて、振り返った。
「この旅か、以前の旅の話を。どうせうずくまって怯えているなら、少しは気晴らしをした方がいい」
「……次はって、何も話なんてしてなかったですよね」
わたしの反論は、ほとんど暴風に吹き散らされてしまったように思えたが、冒険者は薄笑いで言い返してきた。
「シルヴィが聞いていなかっただけさ。ねえ、そうだろう、聴衆たるかもめたちよ」
「かもめ?」
わたしは景色に目を凝らした。確かに海が見えるから、遠くには飛んでいるのかも知れない。が、風のせいで、あまり長く目を見開いてはいられない。わたしに見えたのは、岩棚に立つ長身の冒険者と、眼下に広がる未踏の大地。亀裂の谷と、どこまでも青い空と海。
出発地点からは随分と遠くへきたものだ。最近はすっかり旅に慣れた。街道を行くことにも、険しい自然を踏破することにも。
「シルヴィ」
冒険者が呼んだ。おいで、と手を差し伸べられるが、彼がいるのは崖っぷちだ。配慮が足りない。そんな危ないところまで自力で行けるようだったら、そもそも岩陰で座りこんでいたりしないのだ。
わたしが首を横に振ると、冒険者は苦笑して、数歩、岩棚の縁から離れた。
「そうそう。そこにいてください」
少しだけ風が弱くなった時を見計らって影から這い出す。我ながらよたよたと彼の元までゆくと、冒険者は感心の表情でわたしの頭を撫でた。わたしは振り払おうとしかけ、バランスを崩して転んで死ぬのは嫌なので、両手で彼にしがみついた。
「じゃあ、行こう。話の続きは進みながらでいい」
岩棚の影には、急ではあるけど、気をつければ降りていけそうな場所があった。
手がかり足がかりを探しながら急勾配を降りていく。わたしは下を覗く誘惑を忘れるために、頭の隅で昔のことを思い出す。
この冒険者は初対面から傲岸で、腕の立つ男だった。その時は別の名前を名乗っていたし、今ほど奇妙なことを言ったり、変な道を進もうとしたりしなかったけれど。
一人の道行きに限界を感じて共に旅をする人間を求めていたわたしは、冒険者が集まるという酒場の扉を開けた。何か大きな事件で他の冒険者は出払っていて、ただ一人、カウンターの端で、店主と談笑していたのが彼だった。用件を切り出したわたしに、彼は、しかつめらしく旅路や秘境の危険を散々に脅かしたが、最後には「高くつくよ」とため息をついて、同行を了承してくれた。
わたしたちは何度も冒険を繰り広げた――そう、冒険と呼んで不足のない、危険と脅威に満ちた旅を。地図に残る白紙に、いにしえの遺跡の闇に、山岳の頂上に、密林の奥地に、超えてゆくべき虹の手がかりを探して。旅は死やそれ以上の危険と隣り合わせだった。今ある命は幸運の結果でしかない。何度も失敗を繰り返した。
彼が名前を失ったのも、そうした失敗の一つだった。かつて栄えた帝国の廃都でのことだ。虹の光を閉じ込めた宝石を探す旅だった。都の中には、昔は人間だった影たちが蠢いていたから、見つからないよう気をつけて路地を進んだ。伝説の宝石は確かにあったが、年月と破損によって、四色の光しか中には残っていなかった。持ち主である魔術師の亡霊が、盗人に激怒して追いかけてきた。城門の手前で追いつかれて、魔術師はわたしたちに杖を振り下ろした。杖がぎらぎらと光り、冒険者の体から何か透明なものが抜けだして砕けるのを、彼の影からわたしは見た。
彼が魔術師に宝石を投げ返すと、魔術師は満足そうに哄笑して消えていった。
死人のくせに脅かしてくれたなと冒険者は舌打ちした。わたしは彼を呼ぼうとして、何をされたのか気がついた。直前まで覚えていたはずの彼の名前がすっかり記憶から消えていた。そして彼の輪郭がぼんやりと、まるで都の中を徘徊う影のように滲み始めていた。
取り乱すわたしに、彼は影に溶けていきながら、しかし事もなげに、こんなの新しい名前をつければいいだけだ、と言った。きみが何か考えてくれればいい。
「シルヴィ、下を全然見ないのも危ないよ」
冒険者が言った。わたしははっとして、岩を掴む両手に力を込めた。
「下なんて見たら動けなくなります」
「もう少しがんばれば、また休めるから」
彼の言うとおりだった。また大きな岩が張りだして広い足場になっていた。わたしは一番奥に座り込んで、呼吸を整えた。
景色はさっきとあまり変わらなかった。
ごつごつした岩の足場の向こうに広がる大地。青い空と海。それを見下ろす冒険者。廃都の城門の外で、急な事態と提案に取り乱していたわたしは――ふと、思いついた。魔が差したといってもよかった。いつか旅を終わらせるための誘惑だった。
名前を奪われれば存在を失って影になるなら。名前にそんな力があるなら。その逆は?
「虹の向こうに……」
呟きが漏れた。冒険者が振り向いた。彼は疲れ果てたわたしを愉快そうに眺めて、言った。
「もうすぐだ。違ったら、また次の虹を目指せばいい」
「簡単に言いますね」
私はできるだけ不服そうに言い返した。
しかし、旅が以前より容易くなったのは本当だった。相変わらず危険で、酷い目にたくさん遭ったが、目指す場所に辿り着ける頻度は上がっていた。
わたしたちはいくつもの虹を超え、いくつもの世界をめぐった。鋼鉄の文明、凍りついた大地、夜空を埋め尽くす光の都市、偉大な魔法の帝国……わたしたちの旅が尋常のものでなくなったのは、いつからだろうか。少なくとも、あの城門より後のことだ。
――あなたは冒険者。未知と困難に挑む者。あなたの名前は”青い鳥(サリアサリス)”。虹を超え、現実と幻想の狭間を飛ぶ翼。
きみはロマンチストだなと、楽しそうに笑いながら、彼はその名前を認めた。
「さて。口下手なきみにしてはよく語った」
と、背を向けた冒険者が言った。眼下か、空か、どちらかを眺めながら。
「このくらいにしておこう。名残惜しいが尺の都合というものがある。限られた時間で全員が語るからには」
◆
ミードをもう一杯くれないか。いいや、温めなくていい。そのまま注いでくれ。
ありがとう。では残りは手短にいこう。
僕たちは山を降り、平原を進み、巨大な谷へ辿り着いた。
谷は深く、殆ど絶壁に近かったが、いくらかマシな箇所を見つけて、近くの木にロープを結んで地道に降りることにした。
谷底は豊かな森だった。梢から木漏れ日が差し込み、小鳥が頭上でさえずり、人間を知らぬ鹿が、興味津々の様子で僕とシルヴィを見ていた。谷の中央には幅広く清涼な川が、海の方角に向けて流れていた。川にそって歩いていくと、やがて、盛大な水音を上げる滝に行き当たった。高低差は僕の身長の三倍くらいだったか。少し離れた場所を迂廻して、森の中を下り、滝の下へ出た。
ここです、とシルヴィが言った。僕は周囲を見渡しながら頷いた。こんな辺鄙な場所まで辿り着き、五十年に一度だけ虹がかかるなんてことを実際に確かめた暇人が本当に存在するのだろうかと内心で考えながら。
荷物や道程の都合から、半月を逗留期間と決めて、待つことにした。
はじめの二日は何事も起こらなかった。
滝は勢いよく流れ落ちていたが、谷底では光が足りないせいか、虹なんてかからない。
正午頃には中天の太陽は十分な光を落としてくれたものの、角度のせいか、やはり駄目だった。
三日目の昼過ぎ、川上の方角で、何かが爆発するような大きな音がして、すぐに水が濁り始めた。
嫌な予感がして、仕留めて川原で解体しかけの鹿を放って、川遊びをしていたシルヴィを掴もうとしたら、血まみれの手に悲鳴を上げて逃げられた。あっという間に滝の水量が増して、水の壁が落ちてきた。シルヴィは今度は悲鳴を上げてしがみついてきた。
彼女を抱えて鉄砲水に流されながら……というより、川辺の石と岩の上を勢いよく転がされながら、頭上にかかる七色の虹と、青い青い空を舞う、巨大な竜の影を見た。
あれが目覚めて水底から飛び上がるのが五十年ごとだとか、伝承の真相はそんなところだろう。
とにかく、そういう風にして、僕たちはいくつめかの虹を超えた。
◆
雪でますます重くなった扉を、勢いをつけて開け放つと、灯火と熱気が溢れ出てきた。
わたしは想像以上の盛況さに驚いて立ち尽くした。近くにいた誰かが、寒いじゃねえかと怒鳴りかけて、驚いた様子でわたしを見た。それでわたしは我にかえって、慌てて店内に駆け込み、扉を閉めた。
旅の間にすっかり擦り切れてしまったコートを叩く。重い雪がぽとぽと床に落ち、溶けて水たまりになっていく。外にいる間に冷え切っていた指先や耳がちりちりする。
客に料理を運んでいた娘が、足をとめて、わたしを見ている。店内はとても混んでいた――人、人、人でテーブルが埋まり、樽を代わりにしていたり、椅子に料理を置いて床に直で座っている場所もあるような様子だった。
「あの。満席だったらごめんなさい。人を探していて……」
店の娘は「ええと」と言葉を濁し、困惑気味に店の一角を指さした。「あちらの方?」
そちらには赤々と燃える暖炉があり、少し離れたカウンターのとまり木で、探し人である冒険者が長い脚を組んで、杯を片手に、わたしを見ていた。
わたしは彼を呼びながら、早足で近づいていった。少し目を離すとすぐに姿を消してしまう困った人だ。しかも悪びれた様子がない。
「やあ、シルヴィ」
「やあ、じゃないですよ。またふらっといなくなって!」
怒鳴って、ふと気づけば、店内の視線がこちらに集まっていた。思わず気圧され、無言で冒険者に視線で尋ねると、上機嫌な笑顔で答えが返ってきた。
「たわむれの途中だったんだ。どうせ今夜はこの島からは出られない。だから雪がやむまで順番に物語りでもしようって。今、僕の番が終わるところだった」
「百物語みたいなものですか?」
誰かがそんなことを考えついても不思議ではない夜だった。窓の外は一面が雪に閉ざされている。群島地域というらしい辺り一帯には、この季節には、特有の、予想できない吹雪が襲ってくるそうだ。
「確かに、外に出られないから暇でしょうけど、でも、」
「ああ、待って、先に話を締めるから」
冒険者は店内を見渡して、通りのよい声で、少し芝居がかった口調で言った。
「虹を超えた先は確かに別の世界だったが、求める場所ではなかった。だから、彼女の故郷にかかる虹を探して、旅はまだまだ続いているのです。と、こんなところでいいかな?」
「……酔っ払いの与太話に、わたしを使ったんですか!?」
最後の言葉を、カウンターの逆の端にいる奇妙な服装の旅人に投げかける冒険者を、わたしは睨んだ。
彼は残りのミードを飲み干して、とまり木から降りて何枚かの硬貨をカウンターに置き、革鞄を拾い上げた。その足を怒りにまかせて蹴ろうとしたが、避けられた。
「連れが迎えにきたから失礼するよ。楽しい時間を過ごさせてもらった。きみたちの行く手に幸いがあることを祈っている」
彼はわたしの頭を乱暴に撫でて、明るく暖かい店内を縦断していく。
わたしは呆気に取られながら追いかけた。
「し、しばらくは情報収集しながらゆっくりしましょう。奮発して島で一番のホテル取ったんですよ!」
「思う存分ごろごろして、飽きたら出発しよう。吹雪なんて関係ない」
「そうやって自然を軽く見るから、この前みたいなことになるんです」
「何のことかな。せめて店を出るまで格好悪い話は待ってくれ」
軽口を言い合いながら、わたしたちは暖かな店内を後にして、猛吹雪の中に歩み出た。
次の虹を目指す旅の前の、ひとときの休息のために。
◆
そして誰かが扉を開くと、暗く深い夜の底、一面の雪景色だけが広がっていた。