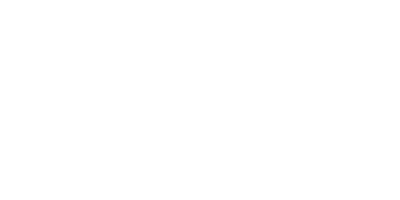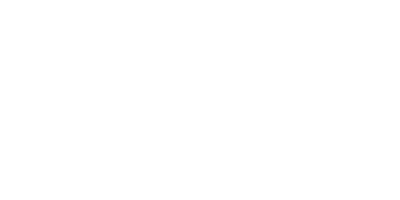私の同僚であるところのS女史の豊かな胸の内側の暗闇には、赤い火が燃えている。
私がそれを知っているのは、美しくも気位の高い彼女と何か特別な関係にあるからというわけではなく、ある些細な偶然のせいだった。その偶然の内容については、この話には大して影響がないので伏せておくことにする。その状況について具体的に誰かに話すようなことをした日には、私はきっとS女史に殺されてしまう――或いは、彼女を崇拝する他の社内の女性達に。
そう、笑える話だが、S女史は、我らがA企画の女神などと呼ばれている。
有能で美しく、誰よりも気性が激しい彼女は、社内からの好悪激しく、崇拝とからかいと揶揄を込めて、誰からともなく囁き出した愛称だ。
その女神様には心臓がない。
白く豊かな二つの膨らみの間にはぽっかりと穴が空いていて、中には、赤い火が燃えている。
私は時々、例えば人材派遣の営業電話を丁寧に断って受話器を置いた後などに、遠く彼女の後ろ頭のてっぺんあたりをディスプレイ越しに眺めながら、その理由について考えてみたりもする。
心臓ははじめからなかったのだろうか、それとも後からなくなったのだろうか。彼女は人間なのだろうか、それとも他の何かなのだろうか。何にせよ、映画かゲームとおなじくらい現実味のない話だ。または、学生の頃に幾らか読んだ、ファンタジー小説か何か。
映画かゲームかファンタジー小説なら、女神の秘密を知ってしまった愚かな男には何か罰があるはずだが、そんなものはもちろんない。
まさか、徹夜明けのプログラマーに「いま代理店から連絡があって、エンドクライアントが勝手に広告打っちゃったから、納期を二週間前倒しにできないかって打診が来てます」と伝えたら肩のあたりを殴られたのが、その罰というわけではないだろう。そもそも、私だってそんなスケジュール変更ができると本気で思って尋ねたわけではないのだ。
その時も、私はS女史の後ろ頭のてっぺんをぼんやりと眺めていた。
私がさほど仕事に熱心でないことは私の周囲の者ならば誰でも知っていたから常であれば咎められることはなかったのだが、その時は、どうもタイミングが悪かった。何かの用事で立ち上がって振り向いたS女史と、まともに視線が合ってしまったのだ。しかも慌てて目を逸らしたのが更に悪かった。
S女史はつかつかと私の元までやってきて、弦楽のような響きの声で言ったのだ。
「何か、わたしにご用ですか?」
「いいえ、とんでもない」
弦楽には十分すぎるほどの棘があった。私は慌てて否定するしかなかった。
いつも彼女を眺めているからには、もし見つかった時にどう誤魔化すべきか、何通りも考えていたのだが、実際に切れ長の目で見下されると、そうした稚拙な言い訳は、言おうと思う端から泡のように弾けて消えてしまった。さすが女神様。なんて迫力だ。
「K通信さんの無茶ぶりをどうしようかと考えてて。どこを見ていたとかじゃないんです。もちろんSさんのことも」
「そう」
S女史は納得したのかしていないのか、形のよい眉毛の間に浅くしわを寄せたまま頷いた。
私はほっとして、彼女の顔を見上げるのをやめた。そして、これは無意識にだが、一瞬、彼女の胸元を見てしまったのだ。身じろぎしたS女史の、その侮蔑の視線といったら! 違うんだ、下心じゃないんだ、とは言い出せず、私はそのあと一日中、気が気でなかった。
そしてあろうことか、定時を二時間過ぎた頃、私が退社しようとした際に、まるで偶然のように彼女は現れた。
節電のために減らされた蛍光灯の下でも、彼女は輝くばかりの存在感があった。立っていても私を見下ろしているのは、ヒールの高いパンプスのせいだろうか。すらりとした灰色のパンツスーツ姿で、土色の革の鞄を肩にかけ、伸ばして左右に分けた前髪の間から、あの切れ長の目が私を見ていた。
「うわあ、Sさん、何かご用ですか」
「ええ、ちょっとね」
それからS女史は半ば強制的に私を連れて、駅の反対側の居酒屋へ入った。「Sさんみたいな美人さんと二人で飲むのは始めてですよ」などという軽口は黙殺された。親睦を深めようという空気ではなかった。
「個室をお願い」と茶髪の店員に告げる彼女の声は、どちらかというと、これから決闘へ赴くのだとでもいった風だった。
「それで」
烏龍茶を二つ、それから串の盛り合わせ、と、S女史が頼んだ色気のない品がテーブルに並んだ。
それを見下ろし、グラスの縁を形の良い爪でなぞってから、彼女は言った。
「あなた、昼間、私の胸を見ていたでしょう」
「やめてくださいよ、セクハラで訴えるのは。本当にわざとじゃないんです」
私は思わずしらばっくれたが、無駄だということはわかっていた。
女がこういう顔をするときは、大抵、私にはもう逃げ場がない時なのだと、大学生の頃に、当時付き合っていた何人かがよくよく思い知らせてくれていた。
実際、S女史は冷たい目で私を見つめていた。居酒屋の薄暗い照明の下、落ちた影に映えるその美しさ。
私は思わず唾を飲み、それからこの後の会話を想像した。想像したところで想像がつくものではなかった。
「実際に見たわけじゃないんです。ただ、聞いたんです。誰から聞いたのかは言えないですけどね」
「……」
この期に及んで嘘だなんて、私はどれだけ愚かなのだろう。
だが本当のことを言ったらそれこそセクハラだ。偶然だと言ったところで通用しまい。
「どうして言えないの」
「約束だからです。私があなたにバレたのは私の自業自得ですけど、まだ上手く隠し通しているあいつを売るわけにはいきません」
「その間に、そのひとは私のことを言いふらしているの?」
あ、まずい。
「私に教えてくれた時は、「お前にしか言わない」って言ってましたよ」
S女史は上品に鼻を鳴らした。なんて器用なんだ、と私は一種の感銘を受けた。さすがは女神様だ。
それから私は、その「誰かから聞いた」ときのつくり話をひと通り話した。我ながら会心の出来栄えで、女神様さえ疑うような表情はしなかった。まあ、土壇場のこれが特技だなんて知れたら、私は社内での信頼を著しく損なうだろうが。
それから店員を呼んで、生、それから枝豆と馬刺し、と告げた。S女史は「アルコールは飲まないの」と言って、オレンジジュースを頼んだ。
それからまた料理が揃うまで幾らかの沈黙があり、二人で黙々と焼き鳥を片付けた。
「それで、信じてる?」
S女史が言った。
私は悩んだ。が、告げた。酒の勢いを借りるにはまだ酔いが足りなかったが。
「ええ、まあ。いくらなんでも、嘘にしてはリアリティがない話です」
「リアリティ、ねえ」
S女史は含み笑いした。初めて見る彼女の私的な表情に思えたが、やはり気位の高い肉食獣のようだった。
その胸の奥では火が燃えている――私はあの日見た輝きを脳裏に浮かべた。白い肌にぽっかりと空いた暗闇。その中で粛々と光る赤い火。それこそリアリティのない光景。同時にどうしようもなく生々しい光。
「私の心臓は、弟にあげてしまったの」
「……は?」
思わずぽかんとした私に、S女史は笑みを深くした。
その美しさといったら。僅かな灯火に照らされた、その瞳の輝きといったら!
S女史はオレンジジュースの禄を撫でて、指先についた水滴を眺めた。
そしてそれをシャツの襟元から覗く白い肌に、ちょん、とつけると、水滴は、ゆっくりと溶け入るようにして消えてしまった。
それを呆然と眺めた後、私はまたS女史の胸元を凝視してしまっていたことに気づいて、慌てて視線を外した。
「子供の頃、親の留守中に、家が火事になった。わたしは弟と一緒に二階で寝ていて、目が覚めた時には、もうすっかり、炎と煙に囲まれてしまっていた。わたしは泣きわめく弟を連れて玄関を目指そうとしたけど、ダメだった。部屋を出た途端に、煙を吸って、気を失ってしまった」
彼女は赤い唇をグラスにつける。白い喉が液体を嚥下する。
私は、彼女の喉を滑り落ちたオレンジジュースが、その胸のうちの火に注がれ、油のように火勢を強めることを想像した。ひとたびだけ垣間見た、あの粛々と燃える美しい光。A企画の女神としか知らぬ、親しくもない女の、気高さと美しさそのもののような。
「気がつけば廊下は火の海だった。外でサイレンが何重にもけたたましく鳴っていた。抱きかかえた弟は、息をしていなかった。わたしは混乱して、弟の胸に耳を押し付けたけれど、もう心臓の音は聞こえなかった」
私はビールを煽りながら思う。炎と煙に囲まれて、髪を振り乱す幼い彼女を。白い肌を赤く染めた炎と、黒く汚した煤のことを。それは恐らく、その時の彼女の苦難からすれば、馬鹿馬鹿しいほど都合の良いところだけを集めた想像だろう。だとしても、私は、その想像をやめられなかった。その想像の景色に比べれば、正に現実で語られる、彼女の過去の話など、どうでもよいと言ってもよかった。
「炎の中では……時に、信じられないことが起こる。あの時のわたしは、まるで夢の中にいるようだった。
わたしはまるで天啓のように閃いた。弟を助けるためには、動かなくなった心臓を取り替えるしかないって。わたしは弟の胸に手を入れて、心臓を取り出した。夢のように簡単にできた。そしてわたしの心臓をおなじように取り出すと、弟のものと交換したの」
「それで、Sさんの心臓は、どうして火になったんです」
「わたしの手元には弟の心臓が残った。けれど、それはもう動いていなかった。だからわたしはそれを炎にくべた。そうすればいいとわかった……だって、夢の中のようだったから。心臓はわたしの手の中で燃えて、赤い火だけが残った。わたしはそれを抱えて、心臓の代わりに胸の中に戻すと、助けを呼ぶために、叫んだ。階下から、わたしたちを助けに来てくれた消防士の声が応えた。そしてわたしと弟は助け出された。買い物に行っていた母が真っ青になってわたしたちを抱きかかえて、無事でよかったと泣いていた」
「リアリティがありませんね」
私は言った。
女神は嗤った。
「ええ、そう。あれからわたしは夢の中を生きているみたい。
まるでわたしに都合のいい、灰色の夢の中をね」
A企画の女神。気位の高い、有能な、美しい女。冗談のように完璧な女。
その豊かな胸元にはぽっかりと黒い穴が空き、中には赤い火が燃えている。
すべてが彼女の夢だとしたら、炎の中、弟を抱いて焼けていく幼い少女の願いだとしたら、いずれ何もかも、炎に焼かれて灰となる。
私たちは、それきり彼女の火の話は終いにして、まるで普通に飲みに来たのだとばかりに仕事の話を幾らか交わし、私の会計で、店を後にした。
会社を出てからまだ二時間を経っていなかったが、長い時間を過ごしたような気分だった。
「今日の話、誰かに言う?」
S女史は言った。
私は笑った。
「まさか。こんな夢のような話、話したところで、私が変人扱いされるだけです」
女神は私のことをまじまじと眺めた後、肉食獣のように唇の端を吊り上げた。
私は牙にかけられた哀れな獲物のような声音で尋ね返した。
「なかなか興味深いお話でしたが、どうして、私に?」
弦楽のような声が答える。棘はなかった。代わりに、十分すぎるほどの熱があった。
ただただ苛烈な、何かに挑むような、剥き出しの火の熱さが。
「あなたも、いつも夢を見ているようだから」
「確かに、社内で私ほど現実と向き合っていない人間はいないでしょうけどね!」
私は一笑に付した。その通りではあったが、きっと、彼女が期待する類の夢ではないはずだった。
私の肋骨の内側には血と肉が詰まっている。彼女のように、得体の知れない綺麗な光で生きているわけではない。私は己をS女史と同類であるとは一切思えなかったし、彼女自身もそうだろう。
ただ、彼女の秘密に気づいてしまったのが、たまたま私だという、それだけのこと。
ああ、だけど、どうか、女神様。あのバレればセクハラ必至の偶然のことだけは、どうかそのまま知らずにいてください。私はまだ炎に投げ込まれたくはない。
私達は改札を通ったところで別れた。彼女がおなじ路線を使っていることを初めて知った。朝になると会社に現れて、夜になるとどこかへ消える、それこそ不思議な女だと思い込んでいたことに、私は気がついて、衝撃を受けた。
翌日以降もS女史は相変わらずA企画の女神だった。その過去を知った罰は私には降りかからなかった。
再度の納期短縮の打診で徹夜明けのプログラマーに掴みかかられたのが、その罰というわけではないだろう。単に、客の担当者が私とプログラマー両方の連絡先を知っているから、「社内でスケジュール調整を試みたけど無理だった」という既成事実を作りたかっただけで、幾ら私が女神様ほどには仕事ができないからといって、哀れなプログラマーを積極的に炎上案件の生贄に捧げようとしたわけではないのだ。
女神様はその様子を遠目に眺めていた。少しばかり呆れているようだった。
その白く豊かな二つの膨らみの間にはぽっかりと穴が空いていて、中には、赤い火が燃えている。
彼女の夢の世界は、まだ焼け落ちず、今日も続いている。